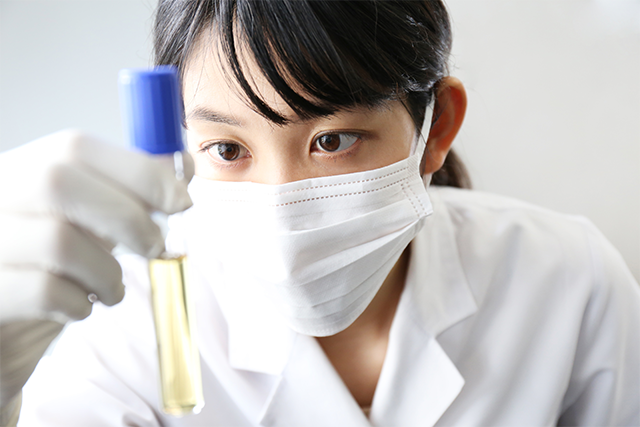
研究者の民間企業でのキャリアパスとは?役立つビジネススキルについても解説
大学の理系学部や大学院(修士・博士課程)で研究に打ち込んできた方にとって、「研究者のキャリアの積み方は?」「自分の専門性は民間企業で通用するのか」「どんなキャリアパスがあるのか」と不安を感じることも珍しくないでしょう。
本記事では、最新の統計や業界動向を踏まえ、理系研究者が民間企業でどのようなキャリアを築けるのか、また、そのために必要なスキルについて体系的に解説します。加えて、キャリア形成を支援するサービス「Laboしごと」の活用方法もご紹介します。
日本総合研究所 創発戦略センター コンサルタント「微生物によるバイオプラスチック生産」を対象とした研究開発の経験を活かし、現職では、政府機関・民間企業に対するバイオテクノロジー・バイオマス由来製品の実装に向けた戦略策定支援、カーボンリサイクル/CCU(Carbon Capture and Utilization)技術の実装に向けた産官学連携のコンソーシアムの企画・運営を担当。著書に「図解よくわかる スマート水産業 デジタル技術が切り拓く水産ビジネス(共著)」「図解よくわかる フードテック入門(共著)」(日刊工業新聞社)。

研究者の主な就職先とそれぞれの特徴
理系研究者の活躍する場は多岐にわたり、「大学」「公的機関」「民間企業」の3つに大別されます。それぞれの特徴を理解し、自分の志向やライフスタイルに合った進路を選ぶことが重要です。
大学
教育と基礎研究を両立できる一方、ポストの少なさや任期付き雇用の多さからキャリアの安定性に課題や不安を感じる方もいます。研究テーマの自由度が高い点が魅力です。
公的機関
国立研究所などでは、社会課題の解決や政策支援を目的とした応用研究が中心です。研究に専念しやすい環境ですが、書類作成や予算申請といった行政的な業務が多くなることもあります。
民間企業
製薬・化学・素材・医療機器など幅広い分野で理系研究者が活躍しています。開発スピードやチーム連携、製品化への意識が求められ、研究成果が短期間で社会実装につながることも多くあります。安定した雇用形態や事業貢献の実感も大きな魅力です。

若手研究者の就職率
大学学部卒以上の研究者にとって、民間企業への就職は有望なキャリアパスの一つです。
文部科学省と厚生労働省が実施した「令和6年度大学等卒業者の就職状況調査(4月1日現在)」によると、大学(学部)全体の就職率は98%、理系学生は97.3%と非常に高い水準です。
また、文部科学省の「大学院関連参考資料集(令和6年7月11日時点)」では、博士過程修了者の約37%が民間企業・公的機関などに、約15%が大学等教員に、約10%がポスドクなどに進んでいます。特に理系の博士課程修了者は、教員以外の専門的職業に従事する割合が高い傾向にあります。
これらのデータから、大学で培われる高度な専門性、実験技術、そして論理的思考力が、民間企業においても高く評価されていることがわかります。
特に博士課程修了者は研究開発や応用研究の現場で即戦力として期待されるため、「民間企業でのキャリアは自分には縁がないかも…」と不安を感じている方にとっても、有力な選択肢となり得るでしょう。

民間企業における多様なキャリアパス
バイオ系研究者の民間企業でのキャリアは多様化しています。研究開発部門に限らず、研究プロジェクトのマネジメントや新規事業の事業企画、アカデミアや他企業との共同研究のような社外連携など、幅広い分野で活躍が可能です。
キャリアパスのイメージ
マネジメント職への移行
研究員として成果を積み上げた後は、プロジェクトリーダーやチームマネージャーとして複数名の研究者を統括し、開発の進行管理や戦略立案を行う立場に進む道も代表的なキャリアの一つです。部門横断の調整や経営陣との連携など、組織運営にも関与するようになります。
専門職(スペシャリスト)として深化
一定の技術分野における高い専門性を武器に、現場の技術的な中核として活躍するキャリアもあります。スペシャリスト制度を設けている企業ではマネジメントの役割を担わずとも、評価され待遇が上がるため、技術志向の強い研究者にとっては魅力的な道です。
他部門や他職種へのキャリアチェンジ
研究開発で培った知見を活かし、製品企画・生産技術・薬事・品質保証・マーケティング部門などに異動し、より事業に近い立場で価値提供を行うパターンもあります。中には営業部門で技術的なサポートを担う「技術営業」へ転向する例もあります。
その他のキャリアパス
事業開発・新規事業創出
近年注目されているのが、研究成果や技術の事業化を担う「事業開発職」です。市場性・社会的意義・ビジネスモデルを評価し、社内ベンチャーやスピンアウト(独立した事業部門や子会社)をリードする役割も含まれます。
R&Dコンサルタント
研究職で培った技術理解と論理的思考力を武器に、他企業や行政の研究開発(R&D)戦略を支援するコンサルタント職に転じる例も増えています。特に、オープンイノベーションを推進する企業や大学でのニーズが高まっています。
アカデミアとの連携(出向・兼業)
一部企業では大学や研究機関へ自社研究者を共同研究のために出向させるケースもあります。こうした「企業に籍を置きつつ、アカデミアと関わる」というハイブリッド型の働き方は、研究者としての成長とネットワーク拡大に寄与します。
大学へ戻る、公的機関へ行く
企業での経験を経て、大学教員や公的研究機関の研究員としてキャリアを再構築するルートもあります。近年は社会実装や産学連携の経験が重視される傾向があることから、企業出身者がアカデミアに戻る例も珍しくありません。
研究内容別で見る!民間企業でのキャリアの方向性
研究者のバックグラウンドはキャリアの出発点に影響します。ここでは基礎研究・応用研究・開発研究それぞれの出身者がどのような役割や職域に展開していくのか、その一例を紹介します。
基礎研究出身者のキャリア
基礎研究出身者はメカニズム解明や仮説構築に強く、企業の研究開発部門でも「探索研究」や「新技術のシーズ開発」において重宝されます。アカデミアに近い知的好奇心と論理構築力を活かし、共同研究や技術戦略策定、将来的にはCTO(技術責任者)候補としての道もあり得ます。
応用研究出身者のキャリア
応用研究経験者は、技術と製品の橋渡しに強みを持ちます。市場ニーズに即した研究設計や、機能性評価、プロトタイプ作成などに長けており、製品開発・技術企画・品質保証・技術マーケティング部門への展開もスムーズです。社内連携や顧客対応の中心となることも多く、マネジメント候補者として期待されるケースもあります。
開発研究出身者のキャリア
開発研究は製品化に直結した工程を担うため、製造部門や営業部門との連携が不可欠です。試作・スケールアップ・コスト管理といった実務能力が求められ、将来的には工場勤務や生産技術のマネージャー職に進むルートもあります。実装力・現場対応力に優れており、事業部側からの信頼も厚いポジションです。

民間企業のキャリアアップで役立つスキル
企業内で研究者としてキャリアを積むには、専門知識に加えて「ビジネススキル」も重要です。以下、求められる6つのスキルを紹介します。
ビジネス化の洞察力
優れた技術を市場の動向や競合環境を踏まえたうえで活かしていくことが重要です。自社のビジネスモデルや業界構造、規制動向を理解し、研究の意義を経営視点から考えられ、ビジネス化するための洞察力を持つ人材は高く評価されます。
コミュニケーション能力
研究成果を他部署や経営層に伝える力はもちろん、チームメンバーとの協働や、他部門との連携、顧客との技術的やり取りも必要です。「分かりやすく伝える力」や「相手の立場を理解する力」が、成果実現の鍵になります。
マネジメント能力
チームやプロジェクトを動かすための計画力・調整力・意思決定力も求められます。研究職であっても予算管理や人材育成を任される場面があり、こうしたマネジメント経験はキャリアアップの大きな武器となるでしょう。
データ分析・可視化スキル
解析ツール(Excel、Python、Rなど)を活用して実験データや業務指標を的確に分析・可視化できる力は、開発スピードや意思決定の質を大きく左右します。仮説検証のプロセスを他者と共有できる資料作成能力も、求められるスキルに含まれます。
プレゼンテーション能力
学会や社内会議だけでなく、製品説明会や顧客向け技術提案など、プレゼンの機会は多岐にわたります。論理的で視覚的にわかりやすい構成、聞き手に合わせた語り方ができることは、研究成果の影響力を高める重要なポイントです。
英語力
国際共同研究や文献調査、海外拠点とのやり取りなど、グローバルな視野での英語対応力も重要です。読み書きはもちろん、会議・交渉レベルでの英会話力を備えておくと、海外プロジェクトに関わるチャンスも掴みやすいでしょう。
まとめ
理系研究者の専門性や論理的思考力は民間企業でも高く評価されており、幅広いキャリアの選択肢があります。自分の強みや志向に合わせてキャリアを柔軟に描くことで、研究を軸に社会とつながる多様な働き方が可能です。
「Laboしごと」では、キャリアに悩む研究者の方が自身の可能性を整理し、納得のいくキャリア選択ができるようサポートしています。まずは自分の専門性や志向を見つめ直し、幅広い選択肢から最適な道を見つけてみてください。

