
バイオ専攻の学生が就職活動で陥りがちな失敗とその対策!
バイオ専攻の学生は高い専門性を持つ一方で、その専門性がかえって就職活動の壁になることがあります。たとえば、「研究内容をうまく伝えられない」「自己PRが印象に残らない」「志望企業の分析が曖昧」といった悩みは、よく見られる傾向です。
本記事では、バイオ専攻の学生に多い就活のつまずきとその原因を解説し、すぐに実践できる改善策をご紹介します。また、バイオ職種に特化した就業支援サービス「Laboしごと」のキャリアサポートを通じて、実務未経験から研究職を目指すためのヒントもお届けします。
日本総合研究所 創発戦略センター コンサルタント「微生物によるバイオプラスチック生産」を対象とした研究開発の経験を活かし、現職では、政府機関・民間企業に対するバイオテクノロジー・バイオマス由来製品の実装に向けた戦略策定支援、カーボンリサイクル/CCU(Carbon Capture and Utilization)技術の実装に向けた産官学連携のコンソーシアムの企画・運営を担当。著書に「図解よくわかる スマート水産業 デジタル技術が切り拓く水産ビジネス(共著)」「図解よくわかる フードテック入門(共著)」(日刊工業新聞社)。

よくある失敗①|研究内容を専門用語で説明しすぎて伝わらない
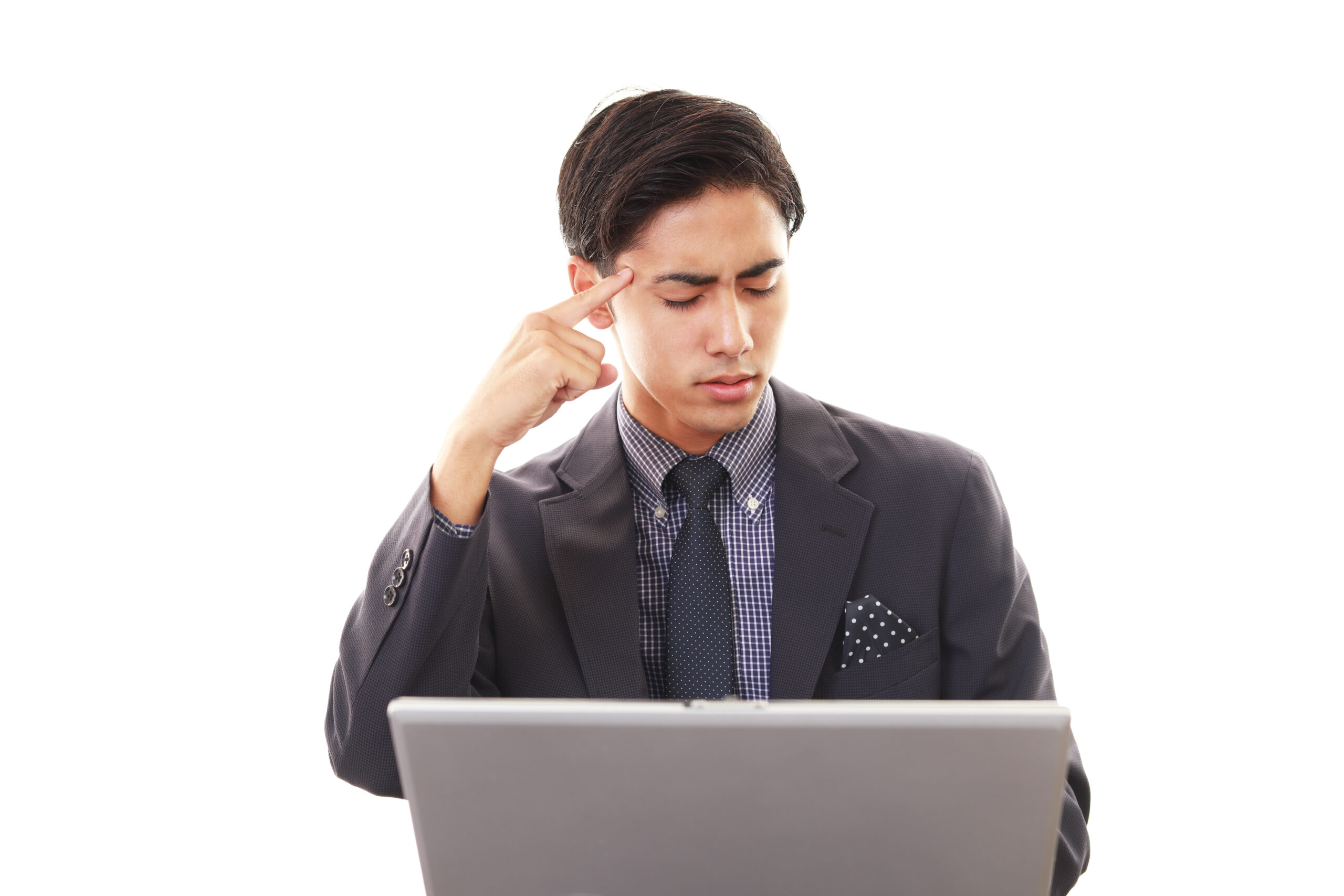
研究職を目指す就職活動において、面接での自己表現は非常に重要です。とくにバイオ系の学生や研究者が見落としがちなのが、「聞き手の前提知識の違い」です。
学会や研究室内での発表は同じ分野の専門家に向けて話すことが多く、専門用語や細かい手法まで掘り下げて説明するスタイルが一般的です。しかし就職活動の面接では、最初に対応するのは多くの場合は人事担当者であり、必ずしも理系やバイオ分野に詳しいとは限りません。
そのため、論文調の説明をそのまましてしまうと、「結局、何を研究していたのか分からなかった」という印象を与えてしまう恐れがあります。面接では、「何のための研究だったのか」「その中で自分は何を学び、どんな力を身につけたのか」を、簡潔かつ人事担当者にも分かるように伝えることが重要です。
対策としては、まず専門外の人にも理解できる言葉に置き換える練習が有効です。専門知識がない友人や家族に話してみて、理解してもらえるか確認しましょう。また、研究内容を1分以内にまとめるトレーニングを繰り返すことで、要点を押さえた話し方が身につきます。
さらに、「Laboしごと」のキャリアアドバイザーに相談すれば、第三者の視点からフィードバックを受けられ、面接に自信を持って臨むためのサポートも得られます。
よくある失敗②|自己PRや志望動機が「研究好き」に偏りすぎている
研究職を志望する多くの学生が口にするのが、「研究が好き」という言葉です。もちろん研究への情熱は大切ですが、それだけでは採用担当者の決め手になりません。企業が重視しているのは、「研究を仕事としてどう捉え、実務にどう貢献できるか」という視点です。
そのため、自己PRでは「実験の失敗から何を学んだか」「困難な課題にどう取り組んだか」といった具体的なエピソードを交えることで、仕事に活かせる姿勢を伝えることが重要です。また、チームでの協働経験や計画的に実験を進めた工夫など、ビジネスに通じるスキルを含めることで、より説得力のあるアピールが可能になります。
採用担当者の視点を意識し、「企業で働く自分」を想像させるような伝え方を心がけることが、評価される自己PRへの第一歩です。
よくある失敗③|研究職に就いて実現したいことが不明確

「研究職ならどこでもいい」というスタンスで企業を選んでしまうと、志望動機が浅くなり、面接でも熱意が伝わりにくくなります。実際には、企業ごとに研究開発の対象分野や業務内容、キャリアパスは大きく異なります。自分に合わない環境は、入社後のミスマッチにもつながりかねません。
対策としてはまず、「どの分野に興味があるのか」「何を研究したいのか」「その先に何を実現したいのか」を言語化することが重要です。その上で、企業ごとの研究テーマや募集ポジションの特性を比較し、自分の志向やスキルに合った企業を選ぶ意識を持ちましょう。
バイオ職種に特化した支援サービス「Laboしごと」では、求人情報の提供にとどまらず、企業の研究開発体制や職種ごとの違いについても詳しくサポートしています。的確な情報をもとに自信を持って志望先を選ぶことが、就職活動成功への第一歩です。
よくある失敗④|面接で緊張しすぎて受け答えがうまくできない
面接でよくある失敗の一つが、緊張のあまり言いたいことがうまく話せなくなるケースです。質問内容は事前に理解していても、いざ本番になると頭が真っ白になった…という経験をお持ちの方も多いでしょう。緊張すること自体は悪いことではありませんが、準備が不十分だとそれが焦りにつながり、伝えたい内容が十分に伝わらなくなってしまいます。
対策として有効なのは、模擬面接による「話す練習」です。特に、「学生時代に力を入れたこと(ガクチカ)」「失敗経験」「将来の目標」といったよくある質問のパターンを押さえ、それぞれの回答を準備しておくことで、本番でも落ち着いて対応できるようになります。
なお「Laboしごと」では模擬面接のサポートも実施しており、実践的なフィードバックを受けられます。自分の課題を客観的に把握し、改善に取り組む過程で、本番に向けた自信を養えます。
よくある失敗⑤|就活準備のスタートが遅れ、インターンや選考に乗り遅れる
「理系は就活のスタートが遅くても大丈夫」と思い込み、インターンや選考のチャンスを逃してしまう学生は意外に少なくありません。とくに研究活動が忙しい理系学生ほど、気づいたときには周囲がすでに動き始めていた、というケースも多く見られます。
就職活動を成功させるカギは、早めの準備。大学3年生や修士1年生の春〜夏の時期から情報収集を始め、インターンや本選考のスケジュールを逆算して「いつまでに何をするか」を計画することが重要です。
また、就活に必要な情報やスケジュール管理のポイントがまとまっている「Laboしごと」を早めに活用すれば、バイオ業界の動向や選考の傾向を把握しやすくなり、スムーズな準備に役立ちます。
まとめ
バイオ専攻の学生が持つ高度な専門性や研究経験は、正しく伝えられれば企業にとって大きな魅力となるでしょう。ただし、どれほど優れた知識・経験があっても、伝わらなければ評価にはつながりません。就職活動では、よくある失敗パターンを事前に把握し、適切な対策を講じることで、選考突破の可能性を高められます。
就活の成功を左右するのは、「自己理解」「企業理解」「伝え方の工夫」の3つです。自分がどのような研究に取り組み、どんな価値を提供できるのかを明確にした上で、それが企業の求める人物像とどう重なるのかを考えることが大切です。
また、「Laboしごと」では、キャリア相談や模擬面接、応募書類の添削などのサポートを無料で受けられます。まずは無料相談を活用して、あなたの強みを一緒に言語化してみませんか?

